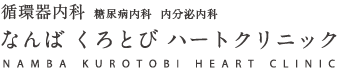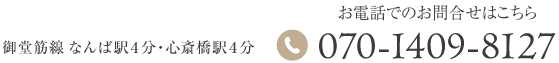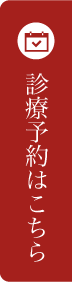院長コラム
Column
流れるいのち
2025年10月27日
2025年10月、大阪・関西万博が幕を閉じました。時間をみつけては度々足を運んだ私にとってもその喪失感で少々寂しいものです。
開催の賛否はありましたが、最終的には大成功のようにも思います。
万博のレガシーは多くの人の心にのこり、これからの国際都市をめざす大阪にとっても大きな自信になったのだと思います。
多種多様なパビリオンの中でも個人的に特に心に残ったのは、万博のメインテーマでもある「いのち輝く未来社会」に正面から取り組んだシグネチャーパビリオン群でした。
そこには、未来の「いのち」への深遠なメッセージが詰まっており、いろいろと考えさせられました。
心に残ったことを少しあげてみますと、まずは肉体からの解放と意識の行方でしょうか。
人間が肉体という制限から解き放たれたとき、”生きる”とは何か?ということを「いのちの未来」のパビリオンでは問いかけます
これは、生前の意識をコンピューターの中に残す技術が現実となった未来を想像させます。
少し先の時代では、人類のあり方を根本から変える大きなテーマとなっているかもしれませんね。
肉体的な死が「いのちの終わり」でなくなったとき、私たちは何を拠り所として「自分」を定義し、未来をデザインしていくのでしょうか。
そして絶え間ない「流れ」としてのいのちについてです。
私たちの体は、一見静止しているように見えても、常に「分解」と「合成」という二つのプロセスを繰り返しながら、釣り合った状態(平衡)でいのちを維持しているのです。
古い水が流れ出て、同時に新しい水が流れ込む噴水のようなイメージです。
噴水の形(体の形)は変わりませんが、中身は絶えず新しいものに入れ替わっています。
流れがないといのちは朽ちてしまうのです。
胃腸の粘膜細胞は数日で、体全体の細胞も約4年から7年でほとんどが新しくなります。
この絶え間ない「流れ」の中にこそ、いのちの本質が宿っています。
この流れがあるからこそ、私たちは常に自己を更新し、イキイキとした体を維持できているのです。
そして「滅びる過程で前進していく」という変化の重要性も訴えかけます。
これは、「終焉や破壊は単なるネガティブな終わりではなく、次のより大きな創造や更新のための必須のエネルギー源である」という考えです。
古いものが滅びることで、新しいものが生まれるスペースとエネルギーが解放され、質的に前進していくことは生物の進化の過程において証明されているのです。
これら思想は、これからの私たちの生き方や将来にも通じます。
過去の慣習や固定観念を壊すことを恐れず、少々の自己犠牲を伴っても将来を思いやる判断こそが、新しい未来への前進につながっていくということなのでしょうか。
万博で提示された「いのち」を巡る問いは、未来をデザインするための議論の種として、これからも生き続けるということなのでしょう。