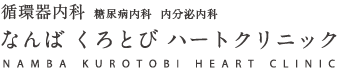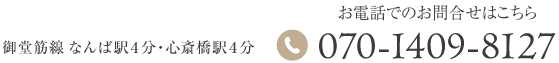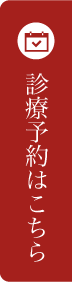院長コラム
Column
働き方
2025年08月29日
新型コロナウイルスの感染の蔓延から職種によっては在宅勤務も広まり、働き方はますます多様になっていくのでしょう。
そして、働き方改革も様々な分野ですすめられています。
「多様でゆとりのある生活を」をスローガンに、時間外勤務や残業も制限されている会社や組織も増えています。
しかし、働く時間が少なくなれば、それだけ効率をあげないと同じ生産性が確保できません。
最近、日本の一人当たりのGDPが欧米のみならず、近隣の国々にも追い抜かれているというニュースを耳にします。
従来、日本独自のハードワークでカバーして海外に対抗してきました。しかし、資源や食料自給率が低く、資源の少ない小さな日本が、豊かな大国とおなじはたらき方をして今後立ちゆくのかということについて、おやじとしてもどうしても一抹の不安を感じてしまいます。
医療についても働き方改革はすすみつつあります。
いままでの医療現場(特に病院勤務)は、献身的な長時間労働で支えられていました。
特に手術や救急対応に対応する現場では、限られた医療資源でぎりぎりでやってきました。医療を守るために。過剰適応せざるをえないという環境であったともいえそうです。
しかし、ハードワワークにも限界があります。私自身、長時間労働と不規則な夜間の当直業務の繰り返しに、このままでは死んでしまうのではないかと生命的な恐怖を感じ、働き方を変えたいと思ったのが40歳手前の時でした。
長期的に医療を維持していくには時代にあわせて働き方を工夫していく必要があるのでしょう。
最近、「直美」を選択する若い医師が増えているということも耳にします(医療の研修はそこそこに直接美容などの自費診療にはいること)。
10年前に比較して、10倍以上にふえているようですね。確かに自費診療の先生は、働く時間は短いが報酬は多いので、効率が高いとも言えます。
私の若い時代は、医療はやりがいがあれば、お金は後回しという文化があったように思います。若い時代に頑張って働けば将来的に報われるものだという、暗黙の了解のようなものもあったようにも思います。
そして時折いただける感謝や敬意が励ましになっていたようにも思います。しかし、それが急速に不信や敵意のようなものにおきかわり、訴訟のリスクもふえてきました。
医療を守るために長期間身を粉にして働いた人が必ずしも報われない、いわゆる効率の悪い姿に若い人は魅力を感じていないということなのでしょうか。
これからの高齢時代、現場の献身的な犠牲に支えられた安価で質の高い医療ということにはそろそろ限界がきているのでしょう。
どのように効率よく手分けするのか?何を捨てて何を残すのか?ということを働き方の改革をきっかけに医療においても考えていく必要があるような気もしています。